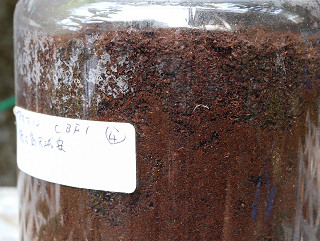| ƒzپ[ƒ€ > ƒRƒEƒ`ƒ…ƒE–ع > ƒNƒڈƒKƒ^ƒ€ƒV‰ب > ƒNƒڈƒKƒ^ƒ€ƒVˆں‰ب |
| ƒAƒ}ƒ~ƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^ | |
| ٹw–¼پFNeolucanus protogenetivus protogenetivus | |
 پ‰57mmپi2023/9/2 “؟”V“‡ژY/F2پj |
| Data | |||||||||||||||
| کa–¼ | ƒAƒ}ƒ~ƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^ پ@•ت–¼پiˆ¤ڈجپjپFƒAƒ}ƒ}ƒ‹ |
||||||||||||||
| ‘ج’· | پ‰پF‚S‚S.‚Rپ`‚U‚T.‚Q‚چ‚چ پٹپF‚S‚Q.‚Oپ`‚T‚Q.‚W‚چ‚چ پ@ژ”ˆç‰؛‚إ‚ح‚U‚X.‚X‚چ‚چ‚ج‹Lک^‚ھ‚ ‚éپB |
||||||||||||||
| •ھ•z | ‰‚”ü‘ه“‡پC“؟”V“‡ | ||||||||||||||
| ڈoŒ»ٹْ | ‚Xپ`‚P‚OŒژ | ||||||||||||||
| ‰a | ‚ب‚µپiژ”ˆç‰؛‚إ‚حچ©’ژƒ[ƒٹپ[‚ًگH‚ׂéپj پ@—c’ژ‚حƒVƒC—ق‚جگش•…‚ꂵ‚½ƒtƒŒپ[ƒN‚ًگH‚ׂéپB |
||||||||||||||
| ژُ–½ | ‚Qƒ–Œژ | ||||||||||||||
| ژ”ˆç“ïˆص“x | ٹب’P پڑپڑپڑپڑپ™ چ¢“ï | ||||||||||||||
| ‰ًگà | ‰‚”ü‚ةگ¶‘§‚·‚éƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^‚جˆêژيپB ‘جگF‚حچ•گF‚إ“ھ•”‚ئ‘O‹¹”w”آ‚ح‚â‚â‰گڈء‚µڈَپBڈممہ‚حŒُ‘ٍ‚ھ‚ ‚èپAچ•گFپ`ˆأٹŒگF‚ـ‚إŒآ‘جچ·‚ھ‚ ‚éپB ‘هŒ^‚ة‚ب‚é‚ھŒ´ژ•Œ^‚ھ‘½‚پAƒ„ƒGƒ„ƒ}ƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^‚âƒIƒLƒiƒڈƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^‚ة”ن‚×پA’·ژ•Œ^‚ح–إ‘½‚ة‚ف‚ç‚ê‚ب‚¢پB گ؟“‡‚ةگ¶‘§‚·‚é‚à‚ج‚ح•تˆںژيƒEƒPƒWƒ}ƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^پiNeolucanus protogenetivus hamaiiپj‚ئ‚³‚êپAٹîˆںژي‚و‚èچX‚ة‰گڈء‚µڈَ‚إپA‘O‹¹”wŒمٹp‘O•û‚ج“ثڈo‚ھژم‚¢‚ب‚ا‚ج“ء’¥‚ھ‚ ‚éپB گ¬’ژ‚حژه‚ة‚XŒژ‚ةٹˆ“®‚·‚éپB —c’ژٹْٹش‚ح’·‚پA‚Sپ`‚T”N‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
|
||||||||||||||
| ژ”ˆçƒپƒ‚ |
‚Q‚O‚Q‚P”N‚P‚OŒژ‚Q‚U“ْ ‚P—î—c’ژ‚S“ھ‚ًچw“üپBƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹(800ml)پAƒ}ƒbƒg‚حUƒ}ƒbƒgپENƒ}ƒbƒgپEƒ„ƒGƒ„ƒ}ƒ}ƒ‹ƒoƒlƒNƒڈƒKƒ^پiˆب‰؛ƒ„ƒGƒ}ƒ‹پj—c’ژژ”ˆçژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg‚جƒuƒŒƒ“ƒhپBŒŒ“•ت‚ةٹا—‚·‚邽‚كپA‚±‚ê‚ç‚S“ھ‚ح‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ئ‚·‚éپB ‘±‚«‚ً•\ژ¦‚P‚PŒژ‚P‚Q“ْ ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ج—c’ژ‚ًƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚ةƒZƒbƒg‚µ‚ؤˆب—ˆپAڈ™پX‚ةگü’ژ‚ھ‘‚¦‚ؤ‚«‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‘¼‚إژg—p‚µ‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚حگü’ژ‚ھŒ©‚ç‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚©‚çچw“üژ‚جƒ}ƒbƒg‚ة‚¢‚½‚و‚¤‚¾پB •تŒŒ“‚ً“üژè‚·‚邽‚كپA“¯ژY’n‚جƒlƒbƒgƒIپ[ƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ“¯ژY’n‚ج‚Q—î—c’ژ‚S“ھ‚ًچw“üپB—¼ŒŒ““¯ژm‚إƒyƒA‚ھ“¾‚ç‚ê‚ê‚خ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éپB ‚â‚â‘ه‚«‚ك‚جƒvƒٹƒ“ƒJƒbƒv‚ة‚S“ھˆêڈڈ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚S“ھˆêڈڈ‚ةƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ةƒZƒbƒg‚µ‚½پBƒ}ƒbƒg‚ح‚Tٹ„ژ©چى‚جƒXƒ_ƒWƒCگشŒح‚êƒ}ƒbƒgپAژc‚è‚ح‚mƒ}ƒbƒg‚ًژه‘ج‚ة‚tƒ}ƒbƒg‚ئƒ}ƒ‹ƒoƒlŒn—c’ژپEژY—‘ژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg‚ًچ¬‚؛‚½‚à‚ج‚ًژg—p‚µ‚½پB‚½‚¾‚µپAژY—‘‚ةژg—p‚µ‚½ƒ}ƒbƒg‚ح‚ـ‚ء‚½‚ژY‚ـ‚ب‚©‚ء‚½ƒ}ƒbƒg‚ج—¬—p‚إ”نٹr“IگV‘N‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB –{—ˆ‚ح—c’ژژ”ˆç—p‚ةگشŒح‚êƒ}ƒbƒg‚ئ“Y‰ء”چyƒ}ƒbƒg‚ًچ¬‚؛‚ؤ‚P‚©Œژ‚حگQ‚©‚¹‚ؤ“éگُ‚ـ‚¹‚½‚ظ‚¤‚ھ‚و‚¢‚ھپA‰½•ھƒlƒbƒgƒIپ[ƒNƒVƒ‡ƒ“‚إ‚جچw“ü‚ئ‚¢‚¤“sچ‡ڈمپA“üژ肵‚ؤ‚©‚ç‚ج‘خ‰‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚ھ“ï“_‚إ‚ ‚éپB ƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚جƒVƒ‡ƒbƒN‚ً‚إ‚«‚邾‚¯کa‚ç‚°‚é‚و‚¤ƒZƒbƒg‚µ‚½ƒPپ[ƒX’[‚جƒ}ƒbƒg‚ة‘ه‚«‚بŒE‚ف‚ًŒ@‚èپA‚»‚ج’†‚ة—c’ژ‚ھ‚¢‚½ƒ}ƒbƒg‚ًڈ‚µ•~‚«پA‚S“ھ‚ً‚ ‚é’ِ“xٹشٹu‚ً•ھ‚¯‚ؤ”z’u‚µ‚ؤپAژc‚è‚جƒ}ƒbƒg‚إ–„‚ك‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚½پB‚±‚ê‚ç‚S“ھ‚ح‚aƒ‰ƒCƒ“‚ئ‚·‚éپB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ج4‚آ‚جƒ{ƒgƒ‹‘S‚ؤ‚ةƒRƒoƒG‚ھ”گ¶‚µ‚½پBگü’ژ‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھ‚ا‚¤‚â‚çƒRƒoƒG‚ج—c’ژ‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚¾پBچ¬چ‡ƒ}ƒbƒg‚ةژg—p‚µ‚½ژg—pچد‚فƒ}ƒbƒgپENƒ}ƒbƒgپEUƒ}ƒbƒg‚ح‚aƒ‰ƒCƒ“‚ج‘¼پA‘¼‚جƒNƒڈƒKƒ^ژ”ˆç‚ة‚à‘½—p‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚ا‚جƒZƒbƒg‚©‚ç‚àƒRƒoƒG‚ح”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚©‚ç—c’ژچw“üژ‚ةˆêڈڈ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½ƒ}ƒbƒg‚ةƒRƒoƒG‚ج—‘‚©—c’ژ‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB ƒ}ƒbƒg‘SŒًٹ·‚ة‚و‚éٹآ‹«‚ج‹}•د‚ج‰e‹؟‚à”ً‚¯‚½‚¢‚ج‚إپA—ٍ‰»‚جŒƒ‚µ‚¢ڈم‘w•”‚جƒ}ƒbƒg‚ًƒRƒoƒG‚ئ‚ئ‚à‚ةژو‚èڈœ‚«پA‹}ç¯چىگ¬‚µ‚½گشŒح‚êƒ}ƒbƒgژه‘ج‚ةژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg‚ًچ¬چ‡‚µ‚½‚à‚ج‚إ•âڈ[‚µ‚½پB‚½‚¾‚µNo.1پi—c’ژ”شچ†پj‚ح“sچ‡ڈمژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg‚ج‚ف‚ً•âڈ[‚µ‚½پB —c’ژ‚جˆہ”غ‚àگS”z‚¾‚ء‚½‚½‚كپANo.3‚ئNo.4‚جƒ{ƒgƒ‹‚ح’†‘w‚ـ‚إƒ}ƒbƒg‚ًژو‚èڈœ‚¢‚½‚ئ‚±‚ëپA–³ژ–‚ھٹm”F‚إ‚«‚½پB—c’ژ‚حژو‚èڈo‚³‚¸ژو‚ء‚½ƒ}ƒbƒg‚ج•ھ‚¾‚¯‘Oڈq‚µ‚½ƒ}ƒbƒg‚ً•âڈ[‚µ‚½پB چ،ŒمپAƒRƒoƒG‚ج”گ¶ڈَ‹µ‚ً‚±‚ـ‚ك‚ةƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚ؤ‰آ”\‚بŒہ‚è‹ىڈœ‚µ‚و‚¤‚ئژv‚¤پB‰ك‹ژƒRƒoƒG‚ج”گ¶‚ة”Y‚ـ‚³‚ꂽŒoŒ±‚ھ‚ ‚èˆظڈي‚ب”ةگB—ح‚ً’ةٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAچ،‚إ‚حژ؛“à‚ةˆê•C‚جƒRƒoƒG‚à”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢ٹآ‹«‚ھˆغژ‚إ‚«‚ؤ‚¢‚邽‚كپAڈ‚ب‚‚ئ‚à‘¼‚جƒ}ƒbƒg‚ض‚جگN“ü‚¾‚¯‚ح‰½‚ئ‚µ‚ؤ‚à”ً‚¯‚½‚¢پB ƒRƒoƒG‚ھ”گ¶‚µ‚½‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح–ˆ“ْگ”‰ٌ‚±‚ـ‚ك‚ةƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAچ،‚ج‚ئ‚±‚ëƒRƒoƒG‚ح”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚½‚¾پA‚â‚ح‚èگü’ژ‚ئژv‚ي‚ê‚é‚à‚ج‚حˆث‘Rٹm”F‚إ‚«‚é‚ج‚إپAگü’ژ‚ئƒRƒoƒG‚ج—¼•û‚ھ‚¢‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB ‚ا‚؟‚ç‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئگü’ژ‚و‚èƒRƒoƒG‚ج‚ظ‚¤‚ھƒ}ƒbƒg‚ض‚جƒ_ƒپپ[ƒW‚ھ‘ه‚«‚¢‚ئژv‚¤‚ج‚إپAƒRƒoƒG‚جچ¬“ü‚ھڈ‚ب‚”ةگB‚ً—}‚¦‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚إ‚ ‚ê‚خƒ}ƒbƒg‚جڈَ‘ش‚ًˆغژ‚µ‚â‚·‚‚ب‚è‚»‚¤‚¾پB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚جNo.2‚جƒ{ƒgƒ‹‚©‚ç1•C‚جƒRƒoƒG‚ًٹm”FپA‹ىڈœ‚µ‚½پB—\‘zˆبڈم‚ة”گ¶—¦‚ھڈ‚ب‚©‚ء‚½‚ھ–ˆ“ْƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚ؤ‚¢‚½چb”م‚ھ‚ ‚ء‚½پB ٹeƒ{ƒgƒ‹‚ح‘¤–ت‚©‚ç‚ف‚é‚ئƒ}ƒbƒg‚ج—ٍ‰»‚ھ–ع—§‚آ‚ھپAƒ}ƒbƒg‚ًڈ‚µ‚ظ‚¶‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئ“à•”‚ح‚»‚ê‚ظ‚ا‚ج—ٍ‰»‚حٹm”F‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إ‚ـ‚¾•غ‚؟‚»‚¤‚¾پBگü’ژ‚جڈَ‹µژں‘و‚إ‚حپA‚aƒ‰ƒCƒ“‚جƒ}ƒbƒg‚ًژg—p‚µ‚ؤ‚ج‘S“ü‚ê‘ض‚¦‚àŒں“¢‚µ‚½‚¢پB ‚â‚ح‚èƒ}ƒbƒg‚ج—ٍ‰»‚ً•ْ’u‚إ‚«‚ب‚¢‚ھپA‚©‚ئ‚¢‚ء‚ؤƒ}ƒbƒg‚ً100%‘ض‚¦‚邱‚ئ‚ة‚و‚éژ–Œج‚à–h‚¬‚½‚¢‚ج‚إپA100%‘ض‚¦‚ؤ‚àˆہ‘S‚بƒ}ƒbƒg‚ًچى‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚â‚è•û‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAŒ»ڈَƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚إژ”ˆç’†‚جگü’ژ‚ھ”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚aƒ‰ƒCƒ“‚جƒ}ƒbƒg”¼•ھ‚ئپAگV‚½‚ةچىگ¬‚·‚éƒ}ƒbƒg‚ً”¼پX‚إپAچX‚ةƒ}ƒbƒg‚ھˆہ’è‚·‚é‚و‚¤‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚إ4“ھˆêڈڈ‚ةژ”ˆç‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚ـ‚¸گV‚µ‚¢ƒ}ƒbƒg‚جچىگ¬‚حژg—p‚·‚éƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ھژ茳‚ة‚ب‚¢‚ج‚إ“üژèŒم‚جچى‹ئ‚ة‚ب‚éپB Œv‰و‚ئ‚µ‚ؤ‚حگV‚µ‚¢ƒ}ƒbƒg‚ًƒXƒ_ƒWƒC—R—ˆ‚جگشŒح‚êƒ}ƒbƒg6ٹ„پANƒ}ƒbƒg2ٹ„پAUƒ}ƒbƒg1.5ٹ„پAƒNƒڈƒKƒ^ژ”ˆçژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg0.5ٹ„‚إƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ةƒuƒŒƒ“ƒh‚µ‚½ڈَ‘ش‚إ1ƒ–Œژ•ْ’u‚µ‚ؤ“éگُ‚ـ‚¹‚½‚à‚ج‚ًژg—p‚·‚éپB ƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ھ“ح‚¢‚½‚ج‚إ‘پ‘¬ƒ}ƒbƒg‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ‚Pƒ–Œژ‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پBگشŒح‚ê‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚àBE-KUWAڈî•ٌ‚¾‚ئژg‚¦‚é‚à‚ج‚ئژg‚¦‚ب‚¢‚à‚ج‚ھ‚ ‚é‚炵‚پAژ©چى‚ھ‚ا‚؟‚ç‚©‚ب‚ج‚©‚ح’è‚©‚إ‚ب‚¢‚ج‚إگS”z‚إ‚ح‚ ‚éپB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚جƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚جڈَ‹µ‚ح–ˆ“ْ•p”ة‚ةƒRƒoƒGƒ`ƒFƒbƒN‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAگ”“ْ‚ة‚P‰ٌ’ِ“x‚جƒyپ[ƒX‚إ‚ـ‚¾ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€‚ةƒRƒoƒG‚ھگ”•C”گ¶‚·‚éڈَ‹µپB‚½‚¾ƒRƒoƒGگâ–إ‚ـ‚إ‚ ‚ئˆê•à‚ئ‚¢‚ء‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپAگü’ژ‚à”گ¶‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚â‚ح‚èƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ح•K—v‚ئچl‚¦پAƒ}ƒbƒg‚جڈnگ¬‚ج‚Pƒ–Œژ‚ة‚ح‚ـ‚¾ڈ‚µ–‚½‚ب‚¢‚ھپA“~‹x‚ف‚جژٹش‚ً—ک—p‚µ‚ؤƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ً‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚ـ‚¸‚aƒ‰ƒCƒ“‚جƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ًŒ@‚è•ش‚µ‚ؤ‚ف‚½‚ئ‚±‚ëپAƒ}ƒbƒg‚ج‰؛‘w•t‹ك‚ة‚S“ھ‚Q—î—c’ژ‚جڈَ‘ش‚إŒ©‚آ‚©‚ء‚½پB‘O‰ٌ‚ئ“¯—l‚ج‚Q—î—c’ژ‚إ‚ح‚ ‚é‚ھپAڈ‡’²‚ة‘ه‚«‚گ¬’·‚µ‚ؤ‚¢‚½پB ‚aƒ‰ƒCƒ“—p‚ةƒ}ƒbƒg‚ً”¼•ھچجژوŒمپA12/8‚ةچىگ¬‚µ‚ؤگQ‚©‚¹‚ؤ‚¨‚¢‚½ƒ}ƒbƒg‚ًچ¬‚؛‚½‚à‚ج‚إƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ً‚µ‚½پB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚جƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚ًŒ@‚è•ش‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپAچإ‰؛‘w•”‚ج‚ظ‚ع“y‰»‚µ‚½Œإ‚¢•”•ھ‚ةƒgƒ“ƒlƒ‹‚ج‚و‚¤‚ب‹َٹش‚ج“à•”‚ة‚¢‚é‚Q—î—c’ژ‚ھٹm”F‚إ‚«‚½پB‘Sƒ{ƒgƒ‹“¯‚¶ڈَ‹µ‚إ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ئ“¯—l‚ة‘S“ھ–³ژ–‚ةگ¬’·‚µ‚ؤ‚¢‚½پB “–ڈ‰پA‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حƒRƒoƒG‚ئگü’ژ‚جڈœ‹ژ‚ج‚½‚كپAƒ}ƒbƒg‘SŒًٹ·پE‘½“ھژ”ˆç‚·‚é—\’肾‚ء‚½‚ھپAŒ»ڈَ‚جƒ}ƒbƒg‚ئگV‚½‚ة—pˆس‚µ‚½ƒ}ƒbƒg‚جژ؟‚ھ‚ ‚ـ‚è‚ةˆظ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ة‚و‚éƒVƒ‡ƒbƒN‚ج‚ظ‚¤‚ھƒٹƒXƒN‚ھچ‚‚¢‚ئ”»’f‚µپA—c’ژ‚ھ‚¢‚éچإ‰؛‘w‚¾‚¯‚ًژc‚µپAڈم‚©‚çگV‚µ‚¢ƒ}ƒbƒg‚ً•âڈ[‚·‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚½پBƒ}ƒbƒg‚ج”ن—¦‚ئ‚µ‚ؤ‚حگV•iƒ}ƒbƒg‚Xٹ„‚ئٹù‘¶‚ج‰؛‘wƒ}ƒbƒg‚Pٹ„پB ‹°‚炃RƒoƒG‚ح‚ظ‚ع”rڈœ‚إ‚«‚½‚ئژv‚¤‚ھپAگü’ژ‚ئ‚ح‹¤‘¶‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚½‚¾پA‰h—{‰؟‚ئ‚µ‚ؤ‚ح’ل‚¢ƒ}ƒbƒg‚ب‚ج‚إ‘ه—ت”گ¶‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚پAˆ«‰e‹؟‚ح‚ ‚ـ‚è‚ب‚¢‚ج‚إ‹C‚ة‚µ‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚¢پB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚جƒ{ƒgƒ‹‚ح‘O‰ٌ‚جƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚©‚çƒRƒoƒG‚ح”گ¶‚µ‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ھپAٹO‚©‚猩‚ؤ‚©‚ب‚èƒ}ƒbƒg‚ج—ٍ‰»‚ھگi‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚é‚ج‚إپAŒًٹ·—p‚جƒ}ƒbƒg‚ًژ–‘O‚ةژdچ‚ٌ‚إ‚¨‚‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB ƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[‘ه‚ةگشŒح‚ê5LپAN‹y‚رUƒ}ƒbƒg‚ً‚»‚ꂼ‚ê5L“ü‚ê‚ؤ‰ءگ…‚µ‚ؤ‚P‚©Œژڈnگ¬‚ً‘ز‚آ‚±‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚»‚ë‚»‚ëƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ً‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB‚ـ‚¾‚Q—î—c’ژ‚ج‚ـ‚ـ‚إپA‚ا‚جƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚à’ê‚ة‚¨‚èپA‚ ‚ـ‚èˆع“®‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚¾‚ء‚½پBƒ{ƒgƒ‹‚ج—c’ژژü•س‚جŒإ‚ك‚ç‚ꂽ•”•ھ‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚µ‚ؤپA‚»‚ج‘¼‚حٹù‘¶‚جƒ}ƒbƒg‚ئ‚ ‚ç‚©‚¶‚كچى‚ء‚ؤ‚¨‚¢‚½گشŒح‚êژه‘ج‚جƒ}ƒbƒg‚ً”¼پX‚ةچ¬‚؛‚½‚à‚ج‚إƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚µ‚½پB ƒ{ƒgƒ‹‚جٹO‚©‚ç‚R—î—c’ژ‚ج“ھ•”‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚½‚½‚كپA800mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚إ’P“ئژ”ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚é‚`ƒ‰ƒCƒ“‚جƒ{ƒgƒ‹Œًٹ·‚ً‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚S–{‚ئ‚à‚R—î—c’ژ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚P“ھ‚ح‚¤‚ء‚·‚ç‚ئپٹ”ء‚炵‚«‚à‚ج‚ھŒ©‚¦‚½‚½‚كپAƒ{ƒgƒ‹‚جƒTƒCƒYƒAƒbƒv‚ح‚¹‚¸‚ة–„‚ك–ك‚µ‚½پB‘¼‚ج‚R“ھ‚ح1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚ةˆع‚µپAٹù‘¶‚جƒ}ƒbƒg‚ة‚ظ‚ع“¯‚¶“à—e‚إچى‚è’u‚«‚µ‚ؤ‚¢‚½ƒ}ƒbƒg‚ًچ¬‚؛‚½‚à‚ج‚إƒZƒbƒg‚µ‚½پB ‚`ƒ‰ƒCƒ“‚ج1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚ج‚Q“ھ‚ھƒ}ƒbƒgڈم‚ةڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‰h—{‰؟‚ھ‘«‚è‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½‰آ”\گ«‚ًچl‚¦پAƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ٹù‘¶‚جƒ}ƒbƒg‚ة‚tƒ}ƒbƒg‚ئگشŒح‚êƒ}ƒbƒg‚ًƒ}ƒbƒg‚ھڈk‚ٌ‚¾•ھ•âڈ[‚·‚é’ِ“x‚إچ¬‚؛‚ؤ“¯‚¶ƒ{ƒgƒ‹‚إچؤƒZƒbƒg‚µ‚½پB 5/29‚ةƒ{ƒgƒ‹‚جƒTƒCƒYƒAƒbƒv‚ً‚µ‚ب‚©‚ء‚½—c’ژ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚à‚©‚ب‚èƒ}ƒbƒg‚ھ“y‰»‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA‚ظ‚ع“¯‚¶“à—e‚جƒ}ƒbƒg‚إ500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚ةƒTƒCƒYƒAƒbƒv‚µ‚½پB Aƒ‰ƒCƒ“‚ح‚à‚¤‚P“ھ1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚إژ”ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ھپAƒ{ƒgƒ‹’ê–ت‚ة‚¢‚ؤ—ژ‚؟’…‚¢‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚ة‚و‚éƒٹƒXƒN‚àچl‚¦پA‚±‚ج—c’ژ‚جƒ}ƒbƒgŒًٹ·‚حŒ©‘—‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ‚S“ھ‚إ‘½ژ”ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚éƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚جƒ}ƒbƒg‚ھڈk‚ٌ‚إ”¼•ھ‚ظ‚اŒ¸‚ء‚ؤ‚¨‚èپA—c’ژ‚ھ‹‡‹ü‚»‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إƒ}ƒbƒg‚ً’ا‰ء‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB’ا‰ء‚·‚éƒ}ƒbƒg‚ح“ء‚ةچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپA‘¦گب‚إ‚tƒ}ƒbƒg‚ًژه‘ج‚ةƒ}ƒ‹ƒoƒlŒn‚جژg—pچد‚فƒ}ƒbƒg‚ئگشŒح‚êƒ}ƒbƒg‚ً‚»‚ꂼ‚êڈ—تچ¬‚؛‚é’ِ“x‚ة‚µ‚½پB چىگ¬‚µ‚½ƒ}ƒbƒg‚حٹù‘¶‚جƒ}ƒbƒg‚ةچ¬‚؛‚¸ڈم‚ةڈو‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚µ‚½‚ج‚إپA‚»‚ج‚ـ‚ـ—c’ژ‚ھگH‚ׂé‚ـ‚إ‚ةڈnگ¬‚·‚é‚ج‚إ‚ح‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚éپB 1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚إ’P“ئژ”ˆç’†‚ج‚P‚آ‚ة–¾ٹm‚ب•دگF•”‚ھ‚ ‚èپA–ڑ‹ت‚ًچىگ¬‚µ‚½‚ئژv‚ي‚ê‚éپBچإ‹ك‚©‚ب‚èٹˆ”‚ةƒPپ[ƒX‚ًê–‚ء‚½‚肵‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ–ڑ‹ت‚ًچىگ¬’†‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB ‘¼‚جƒ{ƒgƒ‹‚⑽“ھژ”ˆç’†‚جƒPپ[ƒX‚إ‚ح•دگF•”‚ھ‚ب‚¢‚à‚ج‚ج—c’ژ‚ھٹm”F‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚إٹù‚ة–ڑ‹ت‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB ƒKƒTƒSƒ\‚ئ‘ه‚«‚ب‰¹‚ھ•·‚±‚¦‚é‚ج‚إ’T‚µ‚ؤŒ©‚é‚ئ–{ژي‚ج—c’ژ‚ًژ”ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚éƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚إپ‰‚ھƒ}ƒbƒgڈم‚إٹˆ“®‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‘ج’·‚ح57mm‚جŒآ‘ج‚¾‚ء‚½پB 1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚à‚P•Cپ‰‚ھڈo‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚ؤ‚Q•C‚جپ‰‚ًٹm”F‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½پB‹°‚ç‚‘¼‚جŒآ‘ج‚àٹù‚ةگ¬’ژ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¤‚ج‚إ‹x“ْ‚ة‚إ‚àٹm”F‚µ‚½‚¢پB ٹù‚ة‰H‰»‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©ٹm”F‚·‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB ƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚©‚ç‚حٹù‚ةژ©—حƒnƒbƒ`چد‚ف‚جپ‰‚ئپٹ‚ھ‚P•C‚¸‚آ“¾‚ç‚êپA‚P“ھ‚ح‚R—î—c’ژ‚إژ€–S‚µ‚ؤ‚¢‚½پB 1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚إژ”ˆç‚µ‚ؤ‚¢‚½ژc‚è‚R–{‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح–ڑ‹ت‚©‚çپ‰‚جهŒپA‚ـ‚¾‚R—î—c’ژ‚ج‚ـ‚ـ‚ھ‚P•CپA‰H‰»•s‘S‚ً‹N‚±‚µٹù‚ةژ€–S‚µ‚ؤ‚¢‚½پٹ‚P•C‚¾‚ء‚½پB 1500mlƒNƒٹƒAƒ{ƒgƒ‹‚إ‚حگ¬گر‚ھˆ«‚¢Œ‹‰ت‚ئ‚ب‚ء‚½‚ھپAƒ}ƒbƒg‚جگF‚حگ^‚ءچ•‚إپAƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[’†‚ج‚à‚ج‚حگشگF‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAگشŒح‚êƒ}ƒbƒg‚ج”ن—¦‚ھ’ل‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ھŒ´ˆِ‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB ‚ئ‚à‚ ‚ê•تŒŒ““¯ژm‚إƒyƒA‚ة‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邽‚كپAƒuƒٹپ[ƒh‚ة’§گي‚µ‚½‚¢پB ‚»‚ë‚»‚ëŒً”ِ‚³‚¹‚邱‚ئ‚ة‚µ‚½پB‚ ‚ç‚©‚¶‚كچىگ¬‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚½ژY—‘—pƒPپ[ƒX‚ةپٹ‚ً“ü‚êپAپٹ‚ةڈو‚¹‚é‚و‚¤‚ةپ‰‚ً“ü‚ê‚é‚ئ‚·‚®‚ةŒً”ِ‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚½پB ‚µ‚خ‚ç‚‚·‚é‚ئŒً”ِ‚ھٹ®—¹‚µ‚½‚ھپAپٹ‚©‚çڈ¬‚³‚‚ؤچ×’·‚¢”’گF‚جگ¸•ï‚炵‚«‚à‚ج‚ھڈo‚½پBٹm‚©‘O‚ةŒً”ِ‚µ‚½گ¸•ï‚ھڈo‚é‚و‚¤‚بژd‘g‚ف‚¾‚ء‚½‚ئژv‚¤‚ھپAڈ‰‚ك‚ؤ‚جŒً”ِ‚إڈo‚é‚ج‚حژ¸”s‚ب‚ج‚©‚QŒآگ¸•ï‚ً“ü‚ꂽ‚ج‚©‚و‚•ھ‚©‚ç‚ب‚¢پBژY—‘ڈَ‹µ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حچؤ“xŒً”ِ‚³‚¹‚½‚¢پB ژY—‘—pƒPپ[ƒX‚حƒRƒoƒGƒVƒƒƒbƒ^پ[‘ه‚ًژg—p‚µپAƒ}ƒbƒg‚ح—c’ژژ”ˆç‚ةژg—p‚µ‚½ƒ}ƒbƒg‚ًژه‘ج‚ةگشŒح‚êƒ}ƒbƒg‚ئ‚mƒ}ƒbƒgپE‚tƒ}ƒbƒgپEژg—pچد‚ف‹غژ…ƒrƒ“‚جگH‚¢ƒJƒX‚ًچ¬‚؛‚½‚à‚ج‚ًژg—p‚µ‚½پB ƒZƒbƒgˆب—ˆپAƒ[ƒٹپ[‚ھ‚ـ‚ء‚½‚Œ¸‚ء‚ؤ‚¨‚炸ƒ}ƒbƒg‚ة“®‚«‚à‚ب‚¢‚½‚كپAٹm”F‚µ‚½‚ئ‚±‚ëƒ}ƒbƒg“à‚إƒoƒ‰ƒoƒ‰‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB ——R‚ح•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ھƒ}ƒbƒg‚ج“à—eˆب‘O‚ج–â‘肾‚ء‚½‚و‚¤‚¾پB‹ة’[‚ةپ‰‚ة•خ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚½‚كپAپ‰‚¾‚¯‚جژ”ˆç‚إڈI‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚»‚¤‚¾‚ھپA‚»‚ج•ھ‘¼‚جƒ}ƒ‹ƒoƒl‚جژ”ˆç‚ةڈW’†‚µ‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢پB |
||||||||||||||